カラスは「ただのうるさい鳥」じゃない!?
実は脳の構造はサル並みで、道具の使い分けから“未来を見据えた判断”までできる超・高知能生物。
その天才ぶりを証明する12のエピソードをご紹介します!
▶︎この記事でわかること
- カラスが“交通ルール”を理解している!? 驚きの観察記録
- 道具を加工して保管する「鳥の職人」
- 仲間の死から危険を学ぶ“カラスの葬式”とは?
エピソード12連発
1. 赤信号を利用!“クルミ自動クラッシャー”作戦
都市部のカラスの間で観察されている“クルミ割りテクニック”には、人間顔負けの知能が隠されています。
たとえば仙台市や函館市では、カラスが交通量の多い交差点を「道具」として利用する様子が記録されています。
やり方はこうです:
- 横断歩道の手前、車がよく通る場所にクルミをぽとんと置く
- 赤信号で車が止まり、クルミをタイヤで轢いて割る
- 青信号になると、横断歩道を歩いてきて割れたクルミを回収
この一連の行動は偶然ではなく、信号の変化と人間の行動パターンを学習している証拠です。
また、車の流れや人の動きに合わせて“タイミングを見計らう”慎重さも見られ、非常に高度な状況判断能力があると考えられます。

2. 空中投下の応用編
信号がない場所では電柱からクルミを落とす“落下割り”を実施。状況によって手法を使い分ける柔軟さがあるんです。
3. “顔”を忘れない──最長17年のブラックリスト
カラスの記憶力の中でも特筆すべきは、「人間の顔の識別能力」です。
ワシントン大学で行われた有名な実験では、研究者が「怖いマスク」と「普通のマスク」を使って、カラスに対して異なる態度で接しました。
- 怖いマスクをつけた人:ネットでカラスを捕まえる
- 普通のマスクの人:近くを歩くだけで何もしない
その結果、「怖い顔」の人物に対して、カラスたちは執拗に鳴き声をあげて警戒。
さらには、その顔を他のカラスにも“伝達”し、群れ全体で反応するようになったのです。
驚くべきことに──
この記憶は17年後にも継続して確認されました。
つまり「一度敵認定された顔」は、カラスにとって永遠にブラックリスト入りする可能性があるのです。
4. ツール職人:枝を曲げて〝釣り針〟を製造
ニューカレドニアガラスは、餌を取るために葉の枝を加工し、先端をフック状に成形して使用。必要に応じて形状を変えるのも確認されています。
5. 価値ある道具は“保管庫”へ
作ったツールは紛失しないように足で押さえたり、木の隙間にしまったり。道具の“資産価値”を理解しているようです。
6. メタツール問題を即解決
「道具を使って道具を得る」──これは人間でもややこしい概念ですが、カラスはこれを理解し、実行できます。
● ある実験では次のような仕掛けが用意されました:
- 餌が透明な筒の中にある(直接は届かない)
- 筒の近くには「長い棒」があるが、それを取り出すにはさらに「短い棒」で引っ張る必要がある
- つまり、まず短い棒 → 長い棒 → 餌という三段階アクション
結果:
カラスは試行錯誤の末に、すべての段階を正しく実行し、餌に到達しました。
これは「目的のために道具を使い、その道具を得るためにさらに別の道具を使う」=ツールチェイン思考(道具の階層利用)ができるということ。
この問題は、チンパンジーでも難易度が高く、成功率は高くありません。
カラスの知的柔軟性と推論能力がいかに高度かを示す好例です。
7. 未来を見据えた“道具の予約”
将来必要になる道具を、今選んで取っておく──そんな“未来計画”ができることも実験で明らかに。ヒト以外では極めてレアな能力です。
8. “カラスの葬式”で危険を学習
カラスの群れの中では、仲間が死んだ場所に他のカラスたちが集まり、しばしば大騒ぎを起こします。
この“カラスの葬式”とも呼ばれる行動は、長らく謎とされてきましたが、最新の研究により以下のようなことがわかっています。
- 感情表現ではなく、学習行動:
死んだ仲間の周囲に集まることで、「この場所に何か危険があった」と認識します。 - 死骸を運んだ人間に警戒反応:
“死のきっかけ”になった対象を記憶し、将来の警戒対象とする。 - 群れ全体で共有される:
一羽が見たことをきっかけに、群れ全体がその場所を避けるようになる事例もあります。
つまりこの“葬式”は、死を通じてリスクを学習し、仲間と情報を共有する“防災訓練”なのです。

9. 自分の“知識の有無”を判断できる
「見たか見てないか」を選ぶ実験で、見た記憶がないと“パス”を選択。これは“メタ認知”と呼ばれ、非常に高度な知性の証です。
10. 再帰構造(入れ子文法)を理解
{ [ ( ) ] } のような入れ子構造(再帰)を正しく処理できる能力も研究で示唆。これは人間の言語構造に近いスキルです。
11. “声でカウント”──1,2,3と鳴き分け
“カァカァカァ”と回数を変えて“数”を伝達。ヒトの子どもが指を折って数えるように、音でカウントする能力が確認されているようですね。
12. 幾何学もOK!図形の規則性を即識別
一見すると抽象的すぎる「図形の対称性」や「幾何学的なパターン」を、カラスは本当に理解できるのでしょうか?
──答えはYes。ある実験では、以下のような課題が出されました:
- 規則正しい図形パターン(例:○△○△○△)と、ランダムな図形列を提示
- どちらが“法則性のある並びか”を選ばせる
結果は驚異的で、人間の幼児並みに高い正答率を示しました。
これはつまり、カラスがただの視覚刺激ではなく、パターン・ルール・違和感の“構造”を理解していることを意味します。
さらに最近では、カラスが「入れ子構造(括弧)」のような再帰文法まで処理できるという論文も発表されており、
論理的・空間的な認識能力は、すでに“飛ぶ哲学者”の域にあると言っても過言ではありません。
カラスの知能はなぜ高いの?
カラスの脳は、哺乳類の“前頭前皮質”に相当する領域が発達。
さらに都市環境・社会性の両方が複雑な問題解決力を要求し、知能の進化を後押ししてきたと考えられています。
ヒトとカラスの上手なつき合い方
- ゴミ出しは朝8時までに・ネットで完全防御
- 黒よりも“透明なゴミ袋”を使うと狙われにくい
- 顔を覚えられたと感じたら、数日は帽子&マスクで“変装”すると効果的!


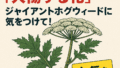
コメント